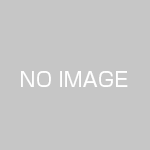前回まで
前回からの続き
交際開始
突然の告白から三ヵ月経過。佳純は浩紀との交際をスタートさせていた。
交際の決め手となったのは、人柄のよさ。この人と一緒にやっていきたいと思わせるものがあった。
浩紀と交際を開始させてからは、週に二~三回くらいのペースでデートする。顔を毎日合わせたいと思うこともあるものの、また会いたいと思えるくらいがちょうどいいのかもしれない。デートを義務だと思うようになると、交際関係は一貫の終わりだ。
デートの場所は交互に決めることで合意した。一方のいきたい場所ばかりにならないよう、気を配っている。
今回は佳純が決める順番となっている。どこに行こうかなと考えていた。
デートをしようと思っても、学校内におけるスポットは非常に限られている。図書館、校庭、教室くらいしかデートスポットはない。
学校外でデートをするという手段もあるものの、帰り道は全く異なっている。家に帰ってから、待ち合わせするというのは現実的ではない。
少ない選択肢から、ここがいいかなと思う場所を選んだ。
「建物の外でデートしようか」
「そうだね」
原則としてデートスポットに異議を唱えることはしない。お互いの意思を尊重する方針を取っている。
校庭では雪が舞っていた。こちらの地方では非常に珍しいといえる。
雪が舞っているだけあって、いつもよりも風は冷たかった。佳純は後者の裏側でデートしたいと伝えた、己の浅はかさを呪った。二人きりになれる場所はいくらでもあった。
浩紀は非常識な場所を選んだ女性を軽蔑していないかな。佳純は恐る恐る視線を向けると、浩紀は白い結晶に目を輝かせている様子が目に飛び込んできた。
「雪はとってもきれいだね」
こちらでは雪の降る機会は非常に限られている。それゆえ、白い結晶に感動するというのはよくある話だ。
佳純は心を動かされることはなかった。雪国に住んでいるわけではないものの、雪は見慣れてしまっていた。日本海に住んでいるおばあちゃんの家を訪ねるときに、一メートルにも及ぶ積雪を目にしたことがある。
太平洋側に住まいを構える人間にとって、日本海側の雪は想像もつかないだろう。同じ日本に住んでいるとは思えないほど、冬の天候は異なる。あちらは雪が降るのに対し、こちらでは太陽が顔をのぞかせている。
佳純の膝下が凍り付きそうなほど、冷たい風に晒される。近年は暖冬傾向にあるとはいえ、二月はさすがに寒かった。
浩紀は膝下をかばうような仕草は見られなかった。学生ズボンをはいているから、冷たさはかなり緩和されていると思われる。女性も冬くらいはズボンを着用させてくれてもいいのに。スケベな男たちが、露出している生足を見るために、スカートをはかせているようにしか思えない。
コートの中からカイロを取り出そうとしていると、浩紀は鞄の中から黒い毛糸上の物を取り出した。
「マフラーを身に着けるといいよ」
浩紀は自分のつけていたマフラーを、佳純の首筋に巻いてくれた。ときおりかすめる、指の温もりが心をポカポカにした。
露出したままの膝下は冷たいままだったけど、大好きな異性の愛情を受け取ることができたのはプラス材料。デート場所としては正しかったのかなと思った。
マフラーの温もりを甘受しようとしていると、浩紀からバレンタインデーの話を持ち出された。
「もうすぐバレンタインだね」
佳純は交際歴がなかったため、バレンタインに特別なイメージを持っていなかった。交際相手のいない男女にとっては、普通の日と何ら変わりない。
市販のチョコレートを渡そうかなと考えていると、浩紀からリクエストがあった。
「佳純、バレンタインに手作りのチョコレートを食べたい」
手作りのチョコレートを渡すシーンを想定していなかっただけに、大いに戸惑ってしまった。塩と砂糖を間違えようものなら、距離は一気に広がってしまいかねない。
チョコレートを楽しみにしている男性に、佳純は料理下手であることを告げる。本来は打ち明けたくないものの、希望で胸を膨らませている男性にきっちりと伝えることにした
「私は天文学的レベルに、料理が下手なの。誰かに食べさせられるような味ではない」
先日はベーコンに砂糖をかけてしまった。そのため、この世とは思えない強烈なインパクトを残すこととなった。砂糖と塩を間違えたチョコレートよりも、ある意味できつかった。
「いいよ。好きな女性のチョコレートなら、すべて完食するよ」
佳純の料理スキルは、男性のハートを一瞬のうちに逃がしてしまうだけの威力を兼ね備えている。浩紀の立場だったなら、破局を視野に入れる。
「どんなにまずくても、嫌いになったりしないでね」
「大丈夫。料理ができないくらいで、嫌いになったりはしないから」
想像を遥かに超えるチョコレートを口にするまでは、安心することはできなかった。佳純はバレンタインの後も、交際関係を継続できるよう、心の中でお祈りした。
「佳純、手を繋ごうよ」
デートにもかかわらず、手ははなればなれになっていた。佳純は自分の左手を、浩紀の右手と重ね合わせる。
手袋をしていたものの、恋人の手の温もりははっきりと伝わってきた。
「浩紀の手はいつもあったかいね」
「佳純も一緒だよ。心がポカポカと温まる」
冬であることをしばし忘れ、デートの余韻に浸っていた。彼氏の存在は、寒さを吹き飛ばすだけの力を備えていた。
冬にこんな温かさを経験できるのは、彼氏と一緒に手を繋いでいるから。好きな人といられるのは心から幸せだと思った。
次回へ続く
文章:陰と陽
画像提供元 https://foter.com/photo4/valentine-heart-romantic-love-girl-tutu/