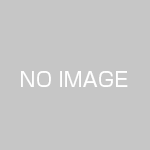第一章 : 突然の出会い
退社して最初に目に飛び込んできたのは、仕事帰りのサラリーマン。彼らもこれから自分の家に帰宅するものと思われる。
枚方市のハローワークの前を通りかかると、私服姿の男女四人ほどが建物をあとにしようとしていた。いつの時代になっても、仕事を探し求める層は一定数存在するのを知った。
椿は利用したことはないものの、いつかはあそこに行くこともありそうだ。どんな気持ちで、求人サイトを閲覧しているのかな。
椿は枚方市駅に向かおうとしていた。会社からは徒歩で一〇分~一五分くらいのところに位置している。
目的地は京橋。特急で一駅となっており、所要時間についてはおおよそ15分。途中の駅に停車しないので、余計な時間を費やさなくて済む。
本日は疲労もたまっているので、8000系列車に連結されているプレミアムカーに乗車しようかなと思った。通常の乗車運賃に400円の追加料金を上乗せされるものの、着席できるメリットは大きい。スペースも広いため、仕事で憔悴しきっているときはオアシスさながらとなる。
2021年1月には特急専用車の8000系だけでなく、3000系にもプレミアムカーを連結する方針。2008年の中之島線開通時は快速急行用として用いられていた、3000系の面影は完全に姿を消すこととなりそうだ。
自宅でゆっくりするところを思い浮かべていると、背中をポンとたたかれた。椿の身体は寒さではなく、恐怖で震えあがることとなった。
顔面から大量の冷や汗が流れている状態で、おそるおそる後ろを振り向いた。誰なのかに注目していると、見覚えのない女性の顔がある。暗闇の中であったため、全体像を完全にとらえることはできなかった。
冷や汗をハンカチで拭ったのち、椿は震えた声で問うた。
「僕に何か用ですか」
警戒で包まれている男性の気持ちなど知る由もないのか、女性は陽気な声で切り出してきた。二人の温度差はマグマと南極くらいの差がある。
「これから、私に付き合っていただけませんか」
椿は新手の詐欺かなと思った。夜の時間帯に男性に声をかけて、法外なお金をだまし取るという事件は後を絶たない。男性側も社会的立場を失うリスクを避けるために、警察に相談するのは難しい。
椿はいつにもなく、あらぶった声を発した。心の中にある恐怖心を一〇〇パーセント隠すことはできなかった。
「僕に気のあるふりをして、お金を騙し取ろうとしているのですか」
女性は意を突かれたのか、あたふたとしていた。
「違います。そういうわけではありません」
「何のために声をかけたのか教えてください」
ここだけははっきりさせておかないと、次に進むこともままならない。椿は納得のいく回答を得られるまで、質問するつもりでいた。
「以前から親しくしたいと思っていたからです。他意はまったくありません」
初対面の男性に対して、親しくなりたいと思うものなのかな。椿は首を大きく横に傾ける。
「どうして親しくなりたいと思ったのですか」
女性は答えを切り出すまでに莫大な時間がかかるかなと予想していたけど、一〇秒もしないうちに回答した。あらかじめこの質問をされることを、想定したのかなと思われた。
「仕事で会社を訪問させていただいたとき、とっても丁寧に対応されていました。私はその姿を見て、親しくなりたいと思うようになりました」
会社にはいろいろな人が訪問するため、一人一人の顔を記憶するのは不可能だ。よっぽど印象のよかった人、二度と来てほしくない人くらいしか頭に残らない。
女性の髪の毛は風に流される。やまとなでしこを想像させるかのようだったので、男として少しだけドキッとしてしまった。
異性との出会いを求めてもそうそう見つかるものじゃない。椿はちょっとくらいなら付き合ってもいいかなと思った。
どのようなところに行くのかなと期待していると、女性は思わぬことを口にした。
「今回は心の準備ができてなさそうなので、次回にしましょう。私は必ず声をかけます」
警戒しすぎたために、絶好のチャンスをつぶすことになってしまった。椿は一人になったあと、どうしてもっと親しくしようとしなかったのかを大いに悔やむこととなった。
第二章 : 再会
帰宅しようとしていると、肩に掌の感覚があった。おふくろの味を連想させるかのような、懐かしさを感じた。
「こんばんは」
声を録音していないにもかかわらず、一週間前の女性だとすぐにわかった。インパクトの強さからか、忘れようにも忘れられない。
「声をかけるといったので、そのとおりにさせてもらいました」
物おじしない性格はとてもうらやましいと思うと同時に、うっとうしさも感じさせた。一歩道を踏み外せば、訴えられてもおかしくないレベルだ。
陽気な声を発していたはずの女性の声から、おおいに緊張しているのを感じ取った。
「今日の都合は大丈夫ですか」
椿はすぐさま問題ないことを伝える。
「大丈夫です」
声をかけてきた女性の瞳は大いに輝いていた。こんなに楽しそうにされると、ちょっとだけ心は和んだ。
カラオケ、ボーリング場、スポーツジムなどの行き先を思い浮かべていると、女性はおなかに手を当てながらいった。
「おなかがすきました。一緒にご飯を食べましょう」
椿はごくごく自然なことに、安心感を覚える。頭の片隅ではキャバクラに誘拐される展開もかすかによぎっていた。その場合は全力で逃げようかなと思っていた。
「いいですけど、どこにしましょうか」
枚方市に向かう途中には多くの店が並んでおり、外食するには困らないと思われる。
松屋の前を通りかかる。女性は手をパンと叩いたのち、椿の服の裾を引っ張った。
「松屋にしましょう」
女性も牛丼などを食べるのか。椿はヘルシーなメニューを好むと思っていただけに意外だった。
こちらとしては特に食べたいものがあるわけではないので、女性の提案に乗っかることにした。
「いいですね」
松屋にめったに行かないので、どのようなメニューがあるのかを知らない。牛丼以外は何を販売しているのかな。
椿は女性と一緒に食事できることに胸を膨らませていた。話すのは得意ではないものの少しくらいは盛り上がるといいな。
次回へ続く
文章:陰と陽