マウリツィオ・ラッツァラート, 杉村昌昭訳『〈借金人間〉製造工場―“負債”の政治経済学』作品社。
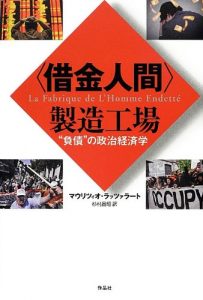
私たちの社会では、「借金は利子を付けて返済しなければならない」ことを自明の前提として受け入れています。
しかしながら、2008年にアメリカで勃発した金融危機(リーマンショック)の際、国家は公的資金を注入して銀行を救済しました。これは、上記に示した自明の前提が崩れ、借金が帳消しになったことを意味しています。
ところで公的資金の流れが、貧困の救済へ向かわずに金融機関へ向かったというのは、もはや、福祉国家のパラドクスといえますが、こうした転倒した社会については、スラヴォイ・ジジェクが自著である『ポストモダンの共産主義――はじめは悲劇として,二度目は笑劇として――』ちくま新書 の中で以下のように述べています。
『「実体経済」ではないものが生命線とは、何とも奇妙なことだ。「実体経済」自体が活力のない死体のようなものだというのか?すると、ポピュリストの掲げるスローガン、「救うならウォール街ではなく目抜き通りを!」はまったくの誤りで、純然たるイデオロギーの一形態ということになる。資本主義のもとで目抜き通りを支えているのはウォール街だという事実を見過ごしている。そのウォール街が倒れたら、目抜き通りはパニックとインフレに襲われることだろう。(P30~P31)』
要するに、負債に対する支払い義務が道徳心を伴って債務者へのしかかるというのは、統治するためのイデオロギーであり、ジジェクの見解に従うと普遍性はないということです。その証左に銀行がデフォルトを起こした際、基本原則が適応されなかったことがあげられるでしょう。
しかしながら、実生活上では負債によって債務者は、あたかも足かせをはめられつつ、僅かな手元金の中から返済し続けていかなければなりません。
完済するまでの間、債権者から半ば自由を奪われる状況に陥るわけですが、これが著者がいうところの「借金人間(ホモ・デビトル)」の実相ということになりましょう。
新自由主義の軸足が金融政策へと向かい、辿り着いた先にあったものが、人々を借金付けにしてしまおうとする強欲な風潮の肯定でした。
やがて最終的には、それが企画化され、ローン生活が社会的に推奨されるように仕向けられていることに繋がっていくのではないか。著者であるマウリツィオ・ラッツァラートは本書で警鐘を鳴らしていました。
文章:justice
