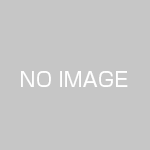前回まで
・小説:『友達のいない男は、クラスメイトの男性恐怖症克服に協力させられた 上』
・小説:『友達のいない男は、クラスメイトの男性恐怖症克服に協力させられた 中』
前回からの続き
屋上での生活
早川と昼休みを一緒に過ごす日々は続いた。
女性と二人きりというシチュエーションに未だに慣れていない。どのように話を持ち掛けていいのか、さっぱりわからない。浩二から話をする機会はほとんどなかった。
早川も無理に話題を持ち出すようなことはなかったので、ときは静かに流れていった。退屈な時間を苦にしているタイプなら、耐えられないのではなかろうか。
早川の男性恐怖症は改善の兆しがみられ、おどおどする機会は減少。最初は青ざめていた顔色も、正常に近づきつつある。
あと一か月もすれば、問題なく男性と話せるようになるのではなかろうか。そうなれば、彼女と一緒にいることもなくなる。非現実的な日々からようやく解放され、心は春を迎えることになりそうだ。
一人になりたいと思っているのに、離れ離れになってしまうことに対する寂しさも感じていた。事情が事情とはいえ、こんなにも一緒にいてくれる人間はいなかった。中学時代までのクラスメイトは、触らぬ神に祟りなしといわんばかりに遠ざけていた。
冬ゆえに冷たい風が突き抜けている。浩二は防寒対策をしていなかったため、身体は大いに震えることとなった。
どのようにして身体を温めようかなと思っていると、早川はスカートのポケットからカイロを取り出した。
「よかったら使わない」
「早川さんは寒くないの」
「カイロを五つくらい持っているから、一つくらいなら大丈夫だよ」
冷たい風に晒されることを見越して、多めに用意してきたのか。準備に抜かりはなさそうだ。
早川は首に巻いていたマフラーも差し出してきた。
「これもよかったら使ってよ」
マフラーを借りるなんてとんでもない、それを口にしようとすると風はヒューヒュー、ヒューヒューと突き抜けた。浩二は冷風に晒されたためか、大きな咳をしてしまうこととなった。
「ヘクチュン」
早川に当たらないように咳をしたものの、風で押し戻されることとなった。小さな心配りは自然の力ではばまれる格好となった。
「早川さん、ごめんなさい」
異物は顔面を直撃していた。そのことに、激怒するかなと思っていると、陽気な笑みをこちらに向けた。
「ううん、気にしなくてもいいよ。マフラー、カイロで温まろう」
早川の掌にあるカイロを受け取ろうとすると、手が重なってしまった。異性の体温を感じるのは初めてのことだったので、大いに動揺することとなった。ドキドキというよりは、はっきりと困惑していた。
「松村君の手は、カイロよりもずっと温かいね」
強姦に遭っても異性と手を重ねられるのかな。男性恐怖症とは乖離しているように見えた。
手を取っているとカップルと間違われてしまいかねない。誤解されないためにも、カイロを受け取ってしまいたいところ。
「もうちょっとだけ・・・・・・」
振りほどいてしまいたい、このままでいたいという二つの相反する感情が交互にやってきた。どうして後半の部分が芽生えたのかというと、二度とこのような展開は訪れないと思ったから。同性とすら親しくできない男性にとって、異性と手を重ね合わせるシーンは奇跡に近かった。
手を重ねていると、扉の開く音がした。こんな状況を目撃されたら、タンポポの種のように噂は拡散しかねない。
誰なのかなと注視していると、屋上にやってきたのは桜田だとわかった。
「葵ちゃんは男子といるとは思えないほど、積極的に過ごしているね」
「松村君は人畜無害だから、安心できるんだ」
浩二だって年代の男子高校生。スイッチが入ったらどうなるかわからない。
「葵ちゃん、二人で話をできるよう席を外してくれる」
「うん、いいよ」
早川の手ははなれてしまった。浩二の手元にはカイロの熱だけが残ることとなった。生身の人間と比較すると、作られたように感じた。
桜田は深々と頭を下げた。
「葵ちゃんを励ましてくれてありがとう。おかげでとっても明るくなった」
少しばかり空を見上げると、世にも珍しいハート型を視界にとらえることとなった。
「葵ちゃんと手を握るなんて、度胸を兼ね備えているんだね」
「カイロを借りようとしたら、重なってしまった。離そうとはしたけど、もうちょっとといわれた・・・・・・」
「そうなんだ。男性恐怖症とは思えないね」
本人に聞くのははばかられるので、一番の親友である女性に質問することにした。
「早川さんのエピソードは実話なのかな。一緒にいると嘘のように感じる」
「強姦に遭ったのはまぎれもない事実だよ。ショックは大きかったのか、一年くらいは不登校の状態だった」
孤独な人生を送ってきた男性よりも、ダメージは大きかったのかな。浩二は登校拒否をしたことは一度もない。
「男子に恐怖心を持っているのに、どうして女子高に行かなかったの」
教師の一部に男が紛れ込んでいるかもしれないけど、基本的には女性に囲まれている。安定した高校生活を送ることが出来るのではなかろうか。
「両親に反対されたみたい。男性恐怖症を克服して、未来につなげてほしかったのかなと思う」
男性を避け続けるのは不可能。両親としては一秒も早い立ち直りを期待していた。
「松倉君と一緒にいたおかげで、かなり改善した。クラスの男子とも少しだけ話せるようになった。彼女からすればものすごい進歩だよ」
「早川さんのことだから、他の男子と親しくなるんじゃない」
桜田は白目を大きく剥いていた。信じられないというような感情が混じっていた。
「松村君は女性の心に鈍感すぎる。対人関係が少ないからしょうがないかなと思う部分はあるんだけど・・・・・・」
早川がこちらに戻ってきた。二人で話しているところに、気が気でないという感じだった。
早川は宙ぶらりんになっている、浩二の掌をつかんだ。先ほどまでは温もりを感じたのに、氷さながらに冷たくなっていた。こちらの手の温度を吸収してしまったのかもしれない。
早川は思いもよらないことを口にした。
「松村君、これからはカップルとしてやっていこうよ」
唐突な展開に頭は追いつかなかった。早川の男性恐怖症を克服したら、終わりだと思っていた。
浩二は手を離してから、率直な心境を伝える。ここにおいては嘘をついてはいけないと思った。
「ごめん、心の整理をする時間を欲しい」
本になじんでいた者にとって、誰かと生活するのはしっくりこない。早川の男性恐怖症より、ずっと根深いものがある。
「私は気長に待っているから、気の向いたときに声をかけてよ」
状況を呑み込めていない男の背中を、桜田がポンと叩く。何かを後押しするかのようだった。
「松村君、鉄は熱いうちに打てというでしょう。今日中には返事をするようにね」
タイムリミットはあまりにも短すぎやしないか。一週間くらいは猶予を与えられると思っていた。
桜田が期限を勝手に設定したことで、早川は胸をときめかせることとなった。
「松村君、今日の放課後に返事を聞かせてね」
一人きりの生活を続けていくのか、早川と一緒の学校生活を送るのか。彼の中ではすでに答えは決まっていた。
冬の風が突き抜ける。一人ぼっちではないからか、少しだけ温かく感じられた。浩二の心の中はすでに春に向けて走り出しているのかもしれない。
完
文章:陰と陽