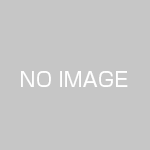大通りを歩く。辺りには通行人に踏みつけられた銀杏の実が、強い匂いを発している。
駅前ビルの方へとわたしは向かった。
すこし肌寒い。
都会の憩いの場としてつくられたらしい「庭園」と称されたスペースに、ぱらぱらと
まばらに男たちがいて、スマホや本を手にしていたり寝ていたりする。
男たちはみな独りでおり、それぞれが適度な距離をたもっている。
楽譜屋が開くまで時間がある。わたしも男たちの群れに混ぜてもらうことにした。
土曜の、朝遅い時間。空はしだいに曇ってきている。
喧噪のエアポケットとしての、都会の憩いの場。それは、家族連れやカップルなどの入る余地のない、おとこたちのやすらぎの場所となっている。
実際、まるでここに入るのに「暗黙の資格」とでも言いうるようなものが必要であるかのようだ。男であること、孤独であること、疲れていること、等々。
この「庭園」がつくられた当初はそんな属性を限定するような意図はあったわけがなく、自然とここを利用するものたちの属性が形作られていった、とでもいうかのようなのである。
庭園とは、消尽されたもののためのある種の理想の楽園であったのだ。
文章:増何臍阿
画像提供元 https://visualhunt.com/f7/photo/14894782238/859712a652/