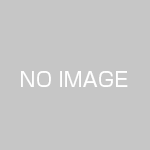大塚沙良は一人の男性に質問を投げかける。
「どうして、心を開かないの」
松本光輝は二度ほど頷いたあと、冷たい口調で答えを返した。
「障碍者にとって、健常者は敵でしかないからね。心を開く必要はないんじゃないかな」
沙良の心臓にぐさりと刺さるものがあった。はっきりと敵といわれるのは想像しなかった。
光輝の目線はいつにもなく鋭かった。普段は怠け者みたいにおとなしいのに、現在は肉食のティラノザウルスさながらに見えた。
光輝はこちらの瞳を覗きつつ、冷たい過去をさらけ出してきた。
「僕は健常者にひどい目に遭わされてきた。そんな人たちと仲良くする必要はあるの」
光輝は目を軽く瞑る。光を受けていない瞳は、人生の希望を失ってしまったかのように映った。
話はさらに大きくなり、健常者を完全否定するようなレベルに到達する。
「健常者は現実を捻じ曲げる、他人を利用する、すねをかじって生きることに関しては超一流だからね。見た目は普通だとしても、中身は完全腐敗しているって言葉がぴったりだよ」
沙良は普段はおとなしく耳を傾けているものの、今回ばかりは黙っていることはできなかった。健常者はそのような人間でないことを伝えた。
「健常者はそんな生き方はしていないよ。誰かのためになろうと必死だよ」
書類の作成、業者とのやり取りなどにおいて汗を流している。障碍者の居場所をよくするために、必死に働いているという自負はあった。
光輝はそっと下を向いたのち、耳をふさぎたくなるような、厳しい言葉を投げかけてきた。
「沙良さんも自分の生き方に違和感を持っていないのか。中身は完全に腐ってしまったんだね」
沙良は体内の怒りを鎮めることに徹した。利用者の前で逆切れしてしまったら、職を失うことになりかねない。
光輝とは関係を壊したくないというのもあった。当人には伏せてあるものの、人間として興味を持っていた。異性としての恋愛感情にまでは達していないものの、距離感を縮めたて
いきたい。
冷静さを取り戻したのち、ソフトな口調で話しかけた。自分は怒っていないというアピールをすることで、スムーズに話を移行させたかった。
「健常者のどこがくるっているのかを話してくれない」
沙良の頬は冷たい弱風にさらされる。厳しい言葉を投げかけられたからか、今回ばかりは強烈なビンタをされたかのように感じられた。
光輝は胸に手を当てていた。苦しいとき、悲しいとき、つらいことを思い出したとき、彼は100パーセント近い確率でこのようにする。
「小学校をたとえにすると、誰かがいじめられていたとする。本来は助けないといけないけど、自分の身を守るために見て見ぬふりをするよね」
この話には思い当たることがあった。保身のために、小学校時代のいじめを黙認していた。
「社会の場では、健常者から役立たず扱いされて退職に追い込まれる。どんなに一生懸命やったとしても、能力不足なら評価されることはない」
そちらについてはイメージがわかなかった。普通に仕事をしていれば、他人から非難されることはない。
光輝は鼻で軽く息を吸っていた。
「障碍者は自分なりにやっていると思うから、健常者からいちゃもんをつけられているように感じる」
障碍者は実害を被っているので、健常者に反感感情を持ちやすくなるのか。これについては避けられない運命なのかもしれない。
「障碍者を見下してきたくせに、生活を守るためだけに障碍者の支援員をやるんだよ。人間としては完全に終わっているレベルだよね。さらにひどくなると、気に入らない利用者を自分の正義のために消去することもある」
そんな支援員はいないと信じたいけど、絶対とは言い切れない。物理解の悪い知的障碍、高齢者を虐待する支援員はいるのではなかろうか。
光輝は脱線しそうになっていた話を戻した。
「人間のあるべき形からずれた生活を送り続けることによって、やってほしいことをする能力を失っていく。善意、悪意であったとしても同じような結果に落ち着く。どっちにしても他人の気分を害することになる」
話を続けたいと思ったものの、光輝は帰宅の準備を始める。本日は奥さんである、麻耶が迎えにやってくる予定になっている。
麻耶と一緒にいるときは、健常者を嫌っているようには見えない。完全なる信頼を寄せているのか、弾けんばかりの笑みを見せる。
麻耶はどのようにして、信用を勝ち取ったのだろうか。沙良は訊いてみたいと思わずにはいられなかった。
暖房はどういうわけかストップする。室内温度はすぐに下がらないはずなのに、心は冷凍庫に入ったかのように冷たくなっていた。
文章:陰と陽
画像提供元 https://foter.com/f5/photo/2694342272/014c96282d/