現象学的な視点のすすめ
著者は哲学の一分野である現象学を専攻する学者で、タイトルからも分かるように、本書は「医療ケア」のアプローチに、現象学の考え方を援用するものとなっています。
さて、読者の中には現象学という言葉に身構えてしまう方もいるでしょうし、ほかにもいくつかの専門用語が出てきますから、そこで挫折しそうになることもあるでしょう。しかし、最初から本書の内容のすべてを逐一理解する必要はありません。哲学の専門家ではない読者は、まず本の中で語られていることの、おおよそのニュアンスをつかむことが出来れば、それで十分だと思います。そうすることで、新しい物の見方が読者に備わり、そこから医療ケアについての新たな視点が開ければ、本書で紹介している他の医療書にも興味が湧いて、徐々に理解を深めていけるはずだからです。
本書の第一章では、「疾患と病い」の副題がついており、まずこの二つの意味の違いから説明していきます。本書によれば、「疾患」とは、『細胞・組織・器官レヴェルでの失調の現れ』。「病い」とは『能力の喪失や機能不全をめぐる人間的経験』と定義付けられます。そうしてこの二つの意味の違いから、現象学への考察へ入ることを試みた本でもあると言えます。
第二章では、現象学の泰斗であるフッサール、ハイデガー、メルロ=ポンティを引用しながら、自説を展開していきます。やはりこの本自体、現象学のことを知らないと、理解が中々深まってこない構成となっていますので、この章ではそれぞれ三人の考え方を丁寧に紹介していました。
計量不可能なことを考えるためのツール
対象を特定化してから治療を施していくことが、西洋医学(アロパシー)の基本ですが、この視点は本書の第一章でいうところの「疾患」となります。一方、「病い」とは、そうした視点を取りません。人間関係やその人自身の体験など、数量化できないことを考えるためのツールが「病い」で、それが本書でいうところの「現象学」の視点ということになります。
要約すると、現象学の方法を取り入れることで、個人の体験を意識化して、さらに自分の物語り(ナラティブ)を紡ぎ出す作業のことに繋がっていきます。したがって、現象学のアプローチでは、客観的で普遍的な構えを取りません。原因・結果で考える科学的視点よりも、関係性に着目しているため、エビデンスに偏らない思考法だと捉えることも出来るところがポイントになっています。
ここまでのことをまとめると、現象学視点を取り入れることによって、個々の患者の意見や体験談を聴くことも、医療従事者にとっては必要だとの方向性で書いている本だというのが、おぼろげながらも理解できるのではないでしょうか。なんとなく肌感覚で分かりますよね。
これを読んでいる皆様にも現象学的視点を知ってほしいのですが、如何せん、人は自分の関心がないことに対しては、なかなか興味を抱きません。
患者をトータルにみる(5つの視点)
第四章の「患者の病いを理解するために」では、パトリシア・ベナー、ジュディス ルーベルの共著『現象学的人間論と看護』の中身を5つの視点に分けて、事細かに解説していきます。ここの章では、ある一人の患者をトータルで理解するための欠かせない視点が下記に示したものだということになります。
1.身体化した知性
2.背景的意味
3.気遣い/関心
4.状況
5.時間制
ちなみに、トータルな観点で患者を捉えようと試みている方法として、本書で扱われている現象学的アプローチ以外にもICF(国際生活機能分類)の概念が有名です。
リハビリテーションとの親和性
以上、本書の紹介をしてきましたが、この他にも人間をトータルで捉えて治療を施していく方法をとっているのがあり、私の考えでは「リハビリテーション」がそれに該当すると思います。
リハビリテーションとは、語源的にはRe(再び)habilis(適する)ation(にすること)で、本来あるべき生活状態を取り戻すことを意味しています。デジタル大辞林によると『身体に障害のある人などが、再び社会生活に復帰するための、総合的な治療的訓練。身体的な機能回復訓練のみにとどまらず、精神的、職業的な復帰訓練も含まれる。本来は社会的権利・資格・名誉の回復を意味し、社会復帰・更生・療育の語が当てられる。リハビリ。』としています。
これは本書の射程範囲には入っていませんが、医療分野におけるリハビリの治療法の中に、現象学の知見が取り入れていることは確かなようです。
『知るとは異なる仕組みで作動する知がある。このとき意識の手前で動いている心のモードを取り出す作業が必要である。実はこの課題は、古くからあり、ほとんど解明の進まなかった課題でもある。』(河本英夫『臨床するオートポイエーシス – 体験的世界の世界と変容』P11より)
インフォーマルを活用した新しい医療ケア
以上、現象学的なアプローチ方法が浸透することで、医療ケアのすそ野が大きく拡がることが期待できますが、それを実践に移すとなると、その人の置かれていたこれまでの境遇にまで配慮しなければならないことになります。要するに、一人に費やされる支援の時間が長くなるというようなことが、懸念材料として残されます。この方法が定着するか否かは、医療費の更なる高騰も招く恐れも含んでいますから、慎重にならざるを得ません。
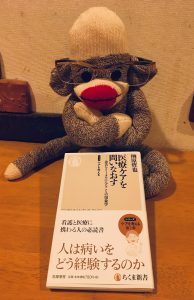
筆者の拙い頭で考える限りでは、その役割を担うのは当事者とインフォーマルな関係性を持った方に絞るべきだと思いました。
最後に、誤解のないように申し添えておきますが、筆者自身は現象学の知識を併せ持った医療従事者が現れることを否定する立場ではないことを表明しておきます。
文章:justice
関連記事

この記事へのコメントはありません。