ケネス・J. アロー『組織の限界』ちくま学芸文庫のレビューです。
和を以て貴しとなす
個人の意思が集まった組織の方が、個人で下した決定より
日本人が昔から引用しているお馴染みの「和を以て貴しとなす」と、どこかで通底しているような言い回しですね。
『エコノミストの目から見れば、それは、集団的行動が個人的合理性の領域を拡張できるからである。』(P20)
ここで言うところの「組織」とは、政府や企業の他、政党
かくして、組織はいかなる個人よりも、より多くの情報を
『かくて権威とは意思決定の集権化であって、情報の伝達と処理についてのコストを節約することに役立つのである 。』(P119)
組織と雖も完璧はあり得ない
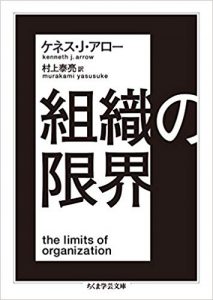
ところでアローの「不可能性定理」とは、個人の意思決定(
ですが本書を読む上で、彼の「不可能性定理」を踏まえる
ですが本書を読む上で、彼の「不可能性定理」を踏まえる
ですから、人為的な社会においては常に「限界」があるこ
※著者であるケネス・J. アローについては、『米国の経済学者。スタンフォード大学教授,ハーバード大学教授。情報の経済学など広範囲にわたる経済理論で業績をあげる。主著は《社会的選択と個人的評価》(1951年)で,個人の合理的判断を集計して社会的判断を形成する際,どんな民主的ルールによる集計でも循環的矛盾を生む可能性を避けられないという,〈一般不可能性定理〉を証明した。この本は後に「社会的選択理論」と呼ばれる分野の先駆的研究となった。一般均衡の存在証明の業績で1972年ノーベル経済学賞。』(百科事典マイペディアより)の経歴を踏んでこられたようです。
文章:justice

この記事へのコメントはありません。