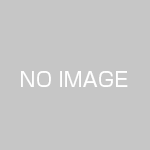「妙に乗客の数がすくないな」
そんなことを思ったのが最初だった。
各駅停車でひとりまたひとりと乗客が降りていく。
気づけば、向こうの端の優先席に座る老人と私だけになっていた。
「おきなさい」
体を揺さぶられて思わずびっくりした。
疲れて寝てしまっていたようだ。目の前には老人がいる。
「たいへんなことになった。早く降りなさい。降りるんだ!」
老人は真剣な眼差しである。鬼の形相で必死に私を電車から降ろそうとする。
そんなことを言われても、電車は走っており駅にはまだ着いていない。
窓から飛び降りろとでも言うのか。
ひと悶着のあと、あきらめた老人はよろよろと向こうの方へと行ってしまった。
その姿を目で追っていたら、隣の車両に移る瞬間老人が消えたような気がした。
何か意識がぼんやりして、また眠ってしまった。
ふと目が覚めると、終着駅のアナウンスが流れた。
ホームに降りると、見たこともない駅だった。
辺りは真っ暗で街灯もほとんどない。相当な田舎のようだ。
古ぼけた駅には駅員も誰もいない。そら恐ろしくなった。
それに、なんだかやたらに冷える。まだ季節は夏から秋にさしかかったところなのに、いったいこの寒さはなんなのだ。
改札はどこかと探すと、ぼんやりした灯りが見えた。待合のようなちいさなスペースだ。
そこに入っていくと、錆びた石油ストーブがあり、傍になにやら老人が杖をつかんで座っている。
老人が顔を上げてこちらを見た。わたしは息をのんだ。
老人の両目が無いのだ。窪んだ眼窩は何もかも吸い込んでしまいそうなほど真っ暗だ。
「早く降りろと言ったのに…」
老人がそう呟くや否や、意識が遠のいていった…
文章:増何臍阿
画像提供元 https://visualhunt.com/f7/photo/20884499720/1f746b9afb/