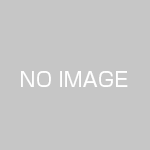はじめに
孤独は、人間に課せられた一種の刑罰である。
刑罰であるなら、それは苦しみでしかない。生が苦そのものであるというのに、どのようにして生を肯定できるのか。
この覚書では、生の否定である反出生主義および自殺について取り上げながら、駆け足ではあるが生を肯定する哲学について考えてみたい。
反出生主義とは
反出生主義とは、出生を否定的に価値づけ子供をもつことを道徳的に悪いことだとする
倫理的見解である。人間が生まれてきたことを否定する思想である。
反出生主義の代表的な擁護者と見られる思想家のエミール・ミシェル・シオラン。
彼は、この世では苦しみは避けられないのだから苦しみが多いほどよく生きたのだという考えや、一冊の書物は延期された自殺である、生誕がそもそものあやまりであるといったことを様々な著書の中で繰り返し述べている。
矛盾の最終的解決としての自殺
ミハイル・バフチンがドストエフスキーを論じるところによると、このロシア作家の中心的思想は「この世では問題の最終的な解決というものはない」というものであるという。
世界は読み解かれるべき一冊の書物であり、ひとりひとりの人間もまた書物である。
先ほどのシオランの言葉によるならば書物は延期された自殺である。であるならば、人間は引き延ばされた死へと向かう存在として、自殺を矛盾の最終的な解決のための手段とする
ことになる。
自殺は、自らの身体はその人の所有物なのだから自由に扱うことができるのか、神に対する罪であるかといった重大な問題を孕んでいる。
希望へ
現代は古代であり、人類が楽園を取り戻す過程における黎明期である(アドルノ)し、先の二つの大戦は、「人類の自己疎外の進行は、自己の殲滅を第一級の審美的快楽とするほどまでになっている」(ベンヤミン)ことを示す現象である。歴史の運動はかずかずの犠牲をその原動力としているとも考えられるし、あるいは歴史はそのひとつひとつの瞬間が希望の門が開かれる可能性をもったものとも考えられる。いずれにしても、希望は必ず存在する。そのために、それがゆえにわれわれの生はつづいていく。
否定弁証法は、あらゆるものを否定に否定を重ねて希望を見出す方法なのだ。
だから、上に挙げた生の否定たちは、生を肯定する為の迂遠な思考たちなのだと私は思う。
さいごに
世界の罪連関への投企は、出生に先立つ罪の存在を暗示している。
罪があるならそれを贖うこともできるはずで、希望があるならば、生き続けることで、その意味を探し求めることができる。希望へと至るながいながい壮大な試みという歴史の中で小さな一個人として生きる。それが生を肯定するということだ。
文章:増何臍阿
画像提供元:https://foter.com/f6/photo/4080981419/1ccb8d4170/