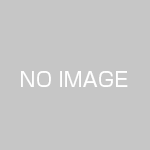幼馴染と決別
前園佳純は幼馴染である、倉橋琢磨の家に遊びにきていた。
小学生を卒業するまでは、毎日のように訪ねていた。異性という認識がなかったためか、男女の壁は存在しなかった。
中学生に入学したあたりから、距離感は変化することになる。互いに異性と認識するようになり、家を訪ねる回数は大幅に減少した。それでも、一週間に一度はプライベートで顔を合わせる。
高校生に進学してからも、二週間に一度くらいの頻度で交流を持っている。たまにしか会わないものの、幼馴染と一緒にいられるだけで心は弾む。
佳純は学生鞄からノートを取り出す。琢磨はこれだけで、何をしようとしているのかを察知した。長年の経験で、おおよそのことはわかるようになっていた。
「佳純、宿題を手伝ってほしいのか」
佳純はペロッと舌を出した。
「ばれっちゃった」
琢磨はやれやれといわんばかりに、両手をあげていた。
「自分で勉強しないと、成績が良くならないぞ」
佳純は幼馴染の肩を強めに叩いた。
「いいの、いいの。学校の勉強に真面目に取り組んでも、将来の役に立たないでしょう」
因数分解、古文、化学などを頭に叩き込ませても、将来の役に立つことはない。学習するだけ時間の無駄だ。
学校ではどうして因数分解、古文、化学、物理、英語といった教科を学ばせるのか。将来のことを考えるなら、職場体験、職場実習、職場見学会といった職場体験の機会を増やしたほうがいい。自分の将来を描くことによって、未来設計を構築しやすくなる。
宿題を教えてもらったこともあり、三〇分としないうちに終えることができた。琢磨は勉強を得意としているわけではないものの、佳純より学力は上である。
「琢磨、ありがとう」
宿題を終えると、勉強道具を鞄に詰め込む。明日の朝まで開かれることはないだろう。
佳純は勉強道具を詰め込むのと入れ替わりに、手作りのチョコレートを取り出す。丹精をこめて作った一品で、幼馴染のハートを鷲掴みしたい。
佳純は中学生にあがったころから、琢磨のことを異性としてみるようになっていた。彼と一緒にいるだけで、胸の鼓動は早くなる。
「琢磨のためにチョコレートを作ってみたの。よかったら食べてみない」
琢磨は手作りのチョコレートと知ったためか、顔がひきつっている。目は完全に死んでいて、生気を感じなかった。
幼馴染の露骨な反応にショックを受けるも、佳純はへこたれなかった。おいしいチョコレートを食べてもらえば、満面の笑みを見せてくれるはずだ。
「琢磨、今回は上手に作ったよ」
佳純を一ミリも信用していないのか、懐疑の視線を向けてきた。
「食べられるような味になっているといいな」
琢磨はチョコレートをおそるおそる齧っていた。毒見をしているかのようなやり方に、佳純はむすっとした。食べるからには、思い切りかぶりついてほしかった。
チョコレートを喉に通した直後だった。琢磨の眉間に皺が大量によっていた。
「しょっぱい」
チョコレートがしょっぱいなんて考えられない。琢磨の味覚は狂ってしまっているのかな。
琢磨は二口目を食べようとはしなかった。丹精を込めて作ったからか、全身は寂しさで包み込まれていた。
「水、水、水をくれ」
佳純が鞄からミネラルウォーターを取り出すと、琢磨は目に止まらぬ速さで奪い取る。その後、豪快に喉に流し込んでいた。
「あー、助かった」
地獄から解放されたことで、琢磨は息を吹き返すこととなった。
「佳純、砂糖と塩を間違えていないか」
料理下手とはいっても、砂糖と塩の区別くらいはつけられる。琢磨の発言にムッとしてしまった。
「そんなはずはないよ・・・・・・」
佳純はチョコレートを齧ると、口の中にあふれんばかりの塩分が広がっていくこととなる。見た目はチョコレートだけど、舌で感じた味は完全に別物だった。
チョコレートのミスを認めたくないからか、佳純は本心とは異なることをいってしまった。
「チョコレートはとってもおいしいよ」
琢磨は信じられなかったのか、目を大きく見開いていた。
「佳純、味覚は大丈夫なのか。病院に行ったほうがいいぞ」
無意味であると知りつつも、虚勢を張り続けることにした。認めてしまったら、数日間の努力は水の泡と化す。
「と、当然じゃない。私の舌に狂いはないわ」
佳純はとっさに思いついたことを話す。これが墓穴を掘ろうことになろうとは、そのときは思ってもみなかった。
「これは塩を訊かせた、塩チョコレートなのよ。琢磨に斬新なものを、食べてほしいという思いで作ったの」
琢磨は疑いのまなざしを向けてきた。
「本当に塩チョコレートなのか」
二つの瞳を見つめられたことにより、心臓の鼓動は早くなっていた。
「当たり前じゃない」
あくまで非を認めようとしない女性に対して、琢磨は塩チョコレートについて説明を加えた。
「塩チョコといっても、塩は少量しか入れない。証拠を見せるから、ちょっと待っていてくれ」
琢磨はスマートフォンをいじりだす。塩チョコレートについて調べて、佳純に見せるつもりのようだ。
検索するまでにかかった時間はおおよそ一分。琢磨はスマートフォンの扱いに長けていた。
「塩チョコレートの作り方はここに書かれている通りだ。塩は少量と書かれている」
実物を見せられてしまっては、勝機はない。佳純はチョコレートの失敗を認めることにした。
「ごめんなさい。塩と砂糖を間違えました」
塩、砂糖の確認はきっちりとしたはず。どこで混入ミスを犯してしまったのか。
琢磨はやれやれといった口調で話をする。
「佳純の料理下手はいくつになっても治らないな」
佳純は右手で後頭部のあたりを掻いた。
「えへへへへ・・・・・・」
卵焼きに、大匙一杯の砂糖を入れる失態を犯したこともある。砂糖を入れすぎたために、完成品は卵焼きではなく甘卵の焼き物だった。
「料理下手は代名詞だからな。これがなくなったら、佳純ではなくなる」
慰めてもらっているのか、けなされているのかはよくわからなかった。佳純は前向きにとらえることにした。
いろいろな会話をしようかなと思っていると、琢磨から話を切り出された。チョコレートの塩味はまだ残っているのか、声はやや霞んでいた。
「佳純、伝えないといけないことがある」
いつにもない真剣さを醸し出していたので、重大発表をする予感がひしめいていた。琢磨は告白をしてくるのだろうか。
自分にとって都合のいい展開を思い浮かべていると、話は思いもよらない方向に進んでいくこととなった。
「白石麻衣さんから、交際を申し込まれた。返事は後日することになっている」
体内の毛が全部抜け落ちそうなほどの衝撃を受ける。琢磨が異性から交際を申し込まれる事態は想定していなかった。
白石麻衣は学校のマドンナ的存在で、狙っている男性はたくさんいる。過去に数えきれないほどの男性がアタックをかけ、撃沈することとなった。麻衣のバリアはかなり固く、誰によって破壊されるのかと噂になっていた。
男性を拒絶し続けた女性の告白相手が幼馴染になるなんて。佳純は自分の運命の針は呪われているのかなと思った。
麻衣との交際をスタートさせたら、琢磨の家にこられなくなる。幼馴染として生きてきた一〇年間は、水の泡と化してしまう。
重大な場面とあってか、口調はいつもよりも強くなっていた。琢磨と疎遠になりたくないという思いが強く滲んでいた。
「琢磨はどうするつもりなの」
一ミリも交際するつもりはないといってくれるかなと思っていたけど、琢磨の答えは異なっていた。
「まだわからない。現状では五分五分といったところかな」
50パーセントも交際する意思を持っていることに、大きなショックを受けることとなった。佳純のことを大事に思っているなら、俺は交際しないというはずだ。
「佳純に交際していいのかを相談したい。おまえならどうする」
好きな異性から恋愛の相談を持ち掛けられるなんて。佳純は現実から目を背けてしまいたかったものの、許される状況にないことは明白だった。
佳純は交際のことで悩んでいる男に対して、本音とは異なることを伝えてしまった。琢磨の本心を知ったことで、投げやりになってしまったのかもしれない。五分五分ではなく、交際しない方向に傾いていれば、違うことをいっていたのではなかろうか。
「交際すればいいんじゃない。私は心から応援しているよ」
私のバカバカバカ。好意を持っている男性を応援する女性がどこにいるんだ。こういうときは、話を無かったように持っていかなければならない。
琢磨は背中を一押しされたからか、すっきりとした表情になっていた。先ほどまで存在していたはずの、迷いは完全に消し飛んでいた。
「佳純、色々とありがとう。おまえもいい男性を見つけて、幸せになれるといいな」
佳純はショックのあまり、放心状態に陥ることとなった。その後はなにをしていたのか、全く覚えていない。
次回へ続く
文章:陰と陽
画像提供元 https://foter.com/f5/photo/33011708418/da9d7ef652/