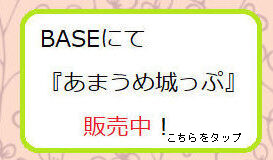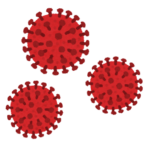前回まで
・小説:『知的障碍を発症した女性は、入院先で少女と出会う 上』
前回からの続き
第二章:入院
優は病気にかかり、病院に入院することになった。入院期間は一〇日間程度を見込んでいる。
病院に入院するのは多くの人にとって苦行だけど、優にとっては楽しみもあった。病院に入院することによって、一般社会に足を踏み入れることを許された。この機会を利用して、健常者の世界観について、細かく観察できればいいな。
隣にネームプレートが貼られていた。名前は「塩崎さくら」となっていた。優は学習能力の低さからか、「塩」、「崎」を読むことはできなかった。特別支援学校とは異なり、ふりがなはふっていなかった。
トイレ、入浴場の案内図もなかった。一般人は地図がなくとも、問題なくできるということか。優は方向音痴で、すぐに道に迷ってしまう。
自分のベッドに戻ろうとしていると、同じ部屋に入院している女性から声をかけられた。
「ねえ、ちょっとだけ話をしようよ」
優はどこにいるのかを探し当てるのに、三分ほどを要することとなった。
一〇歳前後と思われる情緒は、歯にかんだ笑顔を見せる。
「こんにちは」
入院生活は長いのか、顔はやつれていた。表現は悪いけど、くたばりかけの老女さながらだ。
腕には数本の点滴。見るだけで痛々しさが伝わってくるかのようだった。
「おねえちゃんは今日から入院するの」
「うん」
少女はおいでおいでをしたので、優は距離を詰めることにした。
少女は自己紹介をする。ネームプレートに貼ってあるものと同一だった。
「私の名前は塩崎さくら。おねえちゃんが退院するまでの間、私と仲良くしてね」
「うん」
さくらは楽しそうに笑っていた。優は彼女のほほえみを見られるだけで、気分は和んでいた。
「さくらちゃんはいつ退院するの」
一〇歳前後と思われる少女の瞳が曇ることとなった。
「私は病院から解放されることはない。あと一か月しか生きられないの」
「どうして」
さくらは困った顔をしている。よほどいいにくいことなのかなと思った。
少女は小さな声で話した。誰にも知られたくない秘密を、打ち明けているかのようだった。
「身体を病気が蝕んでいるの。どんな手術をしても助からないみたい」
さくらは脇腹を抑える。トラックに突っ込まれたかのように、痛そうにしている。
「イタタタタ」
看護師を呼ぶために、優は室内から飛び出そうとした。さくらは何をしようとしているのかを察し、こちらに引き戻そうとした。
「看護師さんは呼ばなくてもいいよ」
「でも・・・・・・」
「第三者につらいところを見られたくないの」
痛みは軽減されたのか、先ほどよりは幾分苦しさから解放されていた。
「表では優しくしておいて、裏でひそひそしている場面が浮かんでくる。そんな人たちの助けなんかいらないから、潔く天国に行きたいんだ」
少女は笑顔の裏でそんなことを考えていたのか。死への恐怖、病人への差別といった部分を意識するあまり、正常な思考回路を失っているのかもしれない。
優は彼女の気持ちはわからなくもなかった。支援員は表向きでは陽気に接しているものの、裏では障碍者の悪口をいっている。障碍者支援はそういう一面から切っても切り離せない。
さくらは痛みから解放されたのか、陽気な声を発した。
「おねえちゃんは何という名前なの」
「石上優」
「どんな字なの」
石、上については説明できるものの、優の字は無理だった。知的障碍者に、難しい漢字は解説できない。
「私は難しい漢字はわからない」
「そうなんだ」
さくらは一か月後には誰にも話せない身体になる。知的障碍者であることを打ち明けてもいいかなと思った。
「知的障碍って知っているかな。見た目は大きくなっても、肝心の中身は子供のままなんだ」
成長すると他人に分かりにくくなるため、一般人と間違えられることも少なくない。そのことが生きにくさを助長している。
さくらは軽蔑するかなと思っていたけど、反応は真反対だった。
「知的障碍を抱えていても、いいかなって思っている。純粋さはなかなか真似できないよ」
人生で初めて、他人から良いところをほめてもらったような気がする。養育学校に通っていたときは、欠点を重箱のようにつつかれていた。一般人に障碍者の苦労はわからないことは、はっきりとわかった。
さくらは眉間に皺を寄せた。
「大人は汚いから、あんまり好きじゃないの。見た目は健全だけど、中身は青酸カリさながらに腐敗しきっている。触れようものなら、あの世に一直線だよ」
笑顔のとっても素敵な少女が「青酸カリ」という表現を用いたので、優は驚きを隠せなかった。他人を一瞬で死に至らしめる毒物と同じように見ている。
さくらは点滴でつながれていない方の手を、前に出しだした。
「ちょっとだけ手を貸してくれない」
「うん」
優の手を少女は包み込む。手は小さかったものの、優しさを感じさせた。他人を「青酸カリ」扱いするような人間のものとはとても思えなかった。
少女は眠気に襲われたのか、大きなあくびをした。
「身体を休めるために、目をつぶるね」
「うん」
さくらと交わした最後の言葉となった。彼女は一時間後に容態が急変し、集中治療室へと運ばれてしまった。
次回へ続く
文章:陰と陽